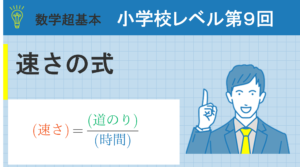【代数学】ウェダーバーンの小定理とは? 強力な主張とシンプルな証明を解説
こんにちは!半沢です!
今回の記事では代数学におけるウェダーバーンの小定理(Wedderburn’s little theorem)について解説します。
その主張は「有限整域は(可換)体となる」といったもので、系として有限な斜体(非可換な可除環)は存在しないことが言えるかなり強力な定理です。
しかし、その証明として群・環・体の基本的な知識があれば理解できるくらいシンプルなものが知られています。
その証明も解説しているので、ぜひ読んでいってください。
ウェダーバーンの小定理(Wedderburn’s little theorem)
ウェダーバーンの小定理(Wedderburn’s little theorem)
有限整域は(可換)体となる。
※以下から、可除環について可換なものを体、非可換なもの斜体と呼ぶことにします。
つまり非可換有限整域は存在しないということですね。
なんとも強力な定理ですね。
系として、有限斜体も、割り算ができ、有限整域であるため、存在しないことも押さえておきましょう。
また、この定理の前提条件が必要最小限であることは次の例から分かります。
例えば有限でない、かつ、整域でない\(\,n\,(\geq 2)\,\)次実行列空間\(\,\mathrm{M}_{n}(\mathbb{R})\,\)は割り算ができないので、体ではありません。
また有限でないが、整域であるハミルトンの四元数体\(\,\mathbb{H}\,\)もあくまで斜体であって、体ではありません。
さらに整域でないが、有限な有限体\(\,\mathbb{F}_{q}\,\)上の\(\,n\,(\geq 2)\,\)次行列空間\(\,\mathrm{M}_{n}(\mathbb{F}_{q})\,\)も、割り算ができないので、体ではありません。
さて、次節からはウェダーバーンの小定理の簡明な証明を確認しましょう。
証明
ここではウェダーバーンによって1905年に初めて証明されてから、
26年後の1931年にヴィット(Witt)が発見したシンプルな証明を紹介します。
群・環・体の基本的な知識があれば理解できます。
有限整域\(\,\Rightarrow\,\)可除環
まずは有限整域が可除環となることを示しましょう。
任意の有限整域\(\,R\,\)を取ってきましょう。
\(0\,\)でない任意の\(\,R\,\)の元\(\,r\,\)について、その逆元の存在を言えば良いですね。
まず\(\,R\,\)は積について閉じているので、\(\,x^1,x^2,\cdots,x^n,\cdots\,\)は全て\(\,R\,\)に属します。
\(R\,\)の有限性から、ある正の整数\(\,i,j\,(i\gt j)\,\)について\(\,x^i=x^j\,\)となります。
式変形をすると\(\,x^{j}(x^{i-j}-1)=0\,\)となります。
\(R\,\)は整域なので、この式から
\(\,x^{i-j}=x\cdot x^{i-j-1}=x^{i-j-1}\cdot x=1\,\)
が得られます。
この式は\(\,x\,\)の逆元が\(\,x^{i-j-1}\in R\,\)となることを意味するので、有限整域\(\,R\,\)は可除環であることが言えました。
※上の「有限整域\(\,\Rightarrow\,\)可除環」であることの証明は、記事公開後に思いついたので加筆したものです。
下に公開当初の証明も載せておきますが、個人的には直感的に分かり易い、かつ、スッキリとした上の証明の方が好きです。
記事公開当初の証明
同様に任意の有限整域\(\,R\,\)について考えます。
この\(\,R\,\)の\(\,0\,\)でない任意の元\(\,a\,\)に対し、\(\,2\,\)つの写像
\(\,f_{L}^{a}:R\to R,\,\, x\mapsto ax\,\)
\(\,f_{R}^{a}:R\to R,\,\, x\mapsto xa\,\)
を考えましょう。
\(a\,\)を左や右からかけるだけですね。
このとき\(\,f_{L}^{a},f_{R}^{a}\,\)はそれぞれ単射になります。
なぜなら例えば\(\,f_{L}^{a}(x)=f_{L}^{a}(y)\,\)とすると、\(\,a(x-y)=0\,\)と式変形できますが、
\(a\not=0\,\)かつ\(\,R\,\)が整域であることから、\(\,x-y=0\Leftrightarrow x=y\,\)となるからです。
単射性と\(\,A\,\)が有限であることから、\(\,f_{L}^{a},f_{R}^{a}\,\)はさらに全射となります。
したがって\(\,a\,\)に対し\(\,f_{L}^{a}(x)=1,f_{R}^{a}(x^{\prime})=1\,\)となる元\(\,x,x^{\prime}\in R\,\)が存在します。
すなわち\(\,ax=1,x^{\prime}a=1\,\)を満たす\(\,x,x^{\prime}\,\)が存在するということで、
正式な用語で言えば、\(\,a\,\)は積に関して左逆元・右逆元を持つことになります。
このとき
\(x=1x=(x^{\prime}a)x=x^{\prime}(ax)=x^{\prime}\)
となり、左逆元・右逆元は一致します。
つまり任意の\(\,a\not=0\,\)に対し、その逆元\(\,x\,(=x^{\prime})\,\)の存在が言えたので、有限整域\(\,R\,\)は可除環であることが言えました。
類等式による考察
前節から、有限整域\(\,R\,\)は可除環であることが言えたので、
後は積について可換であることを言えばよいですね。
そのための一つの道具として、まずは\(\,R\,\)の乗法群\(\,R^{\times}=R\setminus\{0\}\,\)上の類等式を考察していきます。
ひとまず、その準備です。
\(R\,\)の中心環を\(\,Z\,\)、任意の\(\,r\in R\,\)に対し、その中心化環を\(\,Z(r)\,\)と書きます。
\(R\,\)が可除環であることから、\(\,Z,Z(r)\,\)も可除環になることに注意です※1。
さらに中心環\(\,Z\,\)は可換なので体となり、\(\,R\,\)や\(\,Z(r)\,\)へ積を通じて作用できるので、
\(R,Z(r)\,\)は\(\,Z\,\)上のベクトル空間とみなせます。
そのため\(\,|Z|=q\,(\geq 2)\,\)とおくと、
\(|R|=q^{n},|Z(r)|=q^{n_r}\,\,(n,n_r\in\mathbb{N})\,\)と書けます。
\(n=1\,\)となることを示せば、証明は完了することを意識しましょう。
このとき可除環であることから、これらの乗法群の位数は\(\,0\,\)を除いて
\(|R^{\times}|=q^n-1,|Z(r)^{\times}|=q^{n_r}-1,|Z^{\times}|=q-1\)
となります。
これらを乗法群\(\,R^{\times}\,\)についての類等式
\(|R^{\times}|=|Z^{\times}|+\displaystyle \sum_{r\in R^{\times}\setminus Z^{\times}}\dfrac{|R^{\times}|}{|Z(r)^{\times}|}\)
に代入すると
\(q^n-1=q-1+\displaystyle \sum_{r\in R^{\times}\setminus Z^{\times}}\dfrac{q^n-1}{q^{n_r}-1}\)
となります。
ここで類等式の性質から、各\(\,\dfrac{q^n-1}{q^{n_r}-1}\,\)は\(\,1\,\)より大きい自然数になります。
そのため類等式に登場する\(\,n_r\,\)については、\(\,n\gt n_r\,\)という条件が満たされていることに注意しましょう。
また\(\,q^{n}-1\,\)は\(\,q^{n_r}-1\,\)で割り切れることも分かります。
このことから、次のようにして各\(\,n_r\,\)が\(\,n\,\)の約数であることが導けます。
\(n\,\)を\(\,n_r\,\)で割ったときの商を\(\,a\,\)、余りを\(\,b\,\,(0\leq b\lt n_r)\,\)とおくと、
\(n=an_r+b\,\)と書けます。
このとき\(\,(q^{n}-1)-(q^{n_r}-1)=q^{n_r}(q^{(a-1)n_r+b}-1)\,\)も\(\,q^{n_r}-1\,\)で割り切れるはずです。
\(q^{n_r}\,\)は\(\,q^{n_r}-1\,\)と互いに素なので、
これは\(\,q^{(a-1)n_r+b}-1\,\)が\(\,q^{n_r}-1\,\)で割り切れることを意味します。
同様の操作を繰り返すことで、結局\(\,q^b-1\,\)が\(\,q^{n_r}-1\,\)で割り切れることを意味します。
しかし\(\,0\leq b\lt n_r\,\)より、これが成り立つためには\(\,b=0\,\)である必要があります。
以上より余り\(\,b\,\)が\(\,0\,\)となるので、各\(\,n_r\,\)が\(\,n\,\)の約数であることが分かりました。
ここまでのことを一旦まとめましょう。
類等式
\(q^n-1=q-1+\displaystyle \sum_{r\in R^{\times}\setminus Z^{\times}}\dfrac{q^n-1}{q^{n_r}-1}\)
が成り立ち、各\(\,n_r\,\)は\(\,n\,\)の約数である。
※1 \(\,Z,Z(r)\,\)が可除環になることの補足
環になることは一般に言えるので、ここでは可除性のみを補足します。
これは積の逆元を取る操作について閉じていることを言えば良いので、
例えば中心化環\(\,Z(r)\,\)の\(\,0\,\)でない元\(\,z\,\)の、可除環\(\,R\,\)における逆元\(\,z^{-1}\,\)について考えると、
\(r\not=0\,\)のとき
\(z^{-1}r=(r^{-1}z)^{-1}=(zr^{-1})^{-1}=rz^{-1}\)
となり、\(\,r=0\,\)のとき\(\,z^{-1}0=0z^{-1}\,\)は自明なので、どちらにせよ\(\,z^{-1}\in Z(r)\,\)が言えます。
このようにして\(\,Z,Z(r)\,\)の可除性を示せます。
円分多項式による考察
さて続いては前節で確認した類等式を円分多項式を用いてさらに考察し、証明を完成させましょう。
\(m\,\)次円分多項式\(\,\varPhi_m\,\)の性質\(\,x^m-1=\displaystyle\prod_{d\mid m}\varPhi_d(x)\,\)より
よってこれに\(\,q\,\)を代入すると
\(q^n-1=\displaystyle \varPhi_n(q)(q^{n_r}-1)\prod_{d\mid n,d\nmid n_r d\not=n}\varPhi_d(q)\)
となり、円分多項式は係数が整数なので、\(\,\varPhi_n(q),\varPhi_d(q)\in\mathbb{Z}\,\)です。
よってこの式から\(\,\varPhi_n(q)\,\)が\(\,q^n-1\,\)を割り切ることが分かります。
またさらに両辺を\(\,q^{n_r}-1\,\)で割ると、
\(\dfrac{q^n-1}{q^{n_r}-1}=\displaystyle \varPhi_n(q)\prod_{d\mid n,d\nmid n_r d\not=n}\varPhi_d(q)\)
となり、前節より\(\,\dfrac{q^n-1}{q^{n_r}-1}\in\mathbb{Z}\,\)なので、
\(\,\varPhi_n(q)\,\)が\(\,\dfrac{q^n-1}{q^{n_r}-1}\,\)を割り切ることも分かります。
このことと前節より得られた類等式
\(q^n-1=q-1+\displaystyle \sum_{r\in R^{\times}\setminus Z^{\times}}\dfrac{q^n-1}{q^{n_r}-1}\)
から\(\,\varPhi_n(q)\,\)が\(\,q-1\,\)を割り切ることが言えます。
しかし実は\(\,\varPhi_n(q)\,\)が\(\,q-1\,\)を割り切ることは\(\,n=1\,\)のとき以外あり得ません。
なぜなら\(\,1\,\)の原始\(\,n\,\)乗根の集合\(\,\Lambda_n\,\)を用いて\(\,\varPhi_n(q)\,\)は
\(\varPhi_n(q)=\displaystyle\prod_{\lambda\in\Lambda_n}(q-\lambda)\)
と書けますが、\(\,n\gt 2\,\)のとき、各因子に出てくる\(\,1\,\)の原始\(\,n\,\)乗根\(\,\lambda\,\)の実部が\(\,1\,\)より小さいことから、
下の図のように\(\,|q-\lambda|\gt |q-1|\,\)となります。
実際下のように式で厳密に示せます。
そのため\(\,n\gt 2\,\)のとき
\(|\varPhi_n(q)|=\displaystyle\prod_{\lambda\in\Lambda_n}|q-\lambda|>|q-1|\)
となるため、\(\,\varPhi_n(q)\,\)が\(\,q-1\,\)を割り切ることはありません。
したがって\(\,n=1\,\)が帰結され、題意は示されました。\(\quad\square\)
まとめ
今回の記事ではウェダーバーンの小定理(Wedderburn’s little theorem)を解説いたしました。
個人的にはこれだけ強力な定理が、代数学の基本的な知識で導出できることに感銘を受けます。
もし「説明がわかりにくい」などご要望・ご感想がありましたら,
X(旧:Twitter)で#トイカラでつぶやいていただけると,できる限り対応します。
ここまで読んでいただき,ありがとうございました。
参考図書
- \([1]\) Martin Aigner,Günter M. Ziegler.”Proofs from THE BOOK”.Sixth Edition.Springer.2018出版.p.35-38.